SDGs

読売新聞社は教育、福祉など様々な分野で、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいます。

SDG
メディア・コンパクト
SDG
メディア・コンパクト
読売新聞社はSDGsを達成するため、「SDGメディア・コンパクト」に参加しています。
詳しく見るarrow_forward
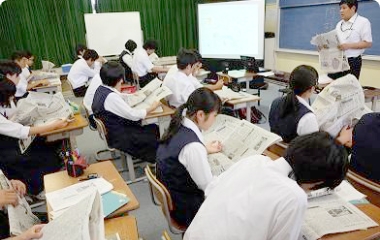
教育・活字文化
教育・活字文化
「読売新聞教育ネットワーク」や「活字文化推進会議」「ビブリオバトル」など、教育や活字文化の振興に取り組んでいます。
詳しく見るarrow_forward
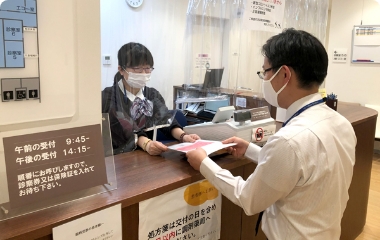
医療・福祉
医療・福祉
「正力厚生会」を通じたがん患者の支援や、医療機関の運営、「読売光と愛の事業団」の活動など、医療・福祉に関する取り組みを紹介します。
詳しく見るarrow_forward

多様性
多様性
読売新聞社は、誰もが働きやすい社会を目指すために、様々な活動を推進しています。
詳しく見るarrow_forward

その他
その他
その他のSDGsに関する取り組みを紹介します。
詳しく見るarrow_forward
